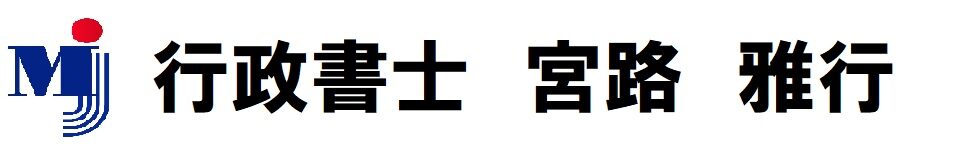そのFC契約書,改正法対応済ですか?-連帯保証人規定-
【改正民法とフランチャイズ(FC)契約書】ー連帯保証人規定ー
こんにちは、所長みやじです。今回は、改正民法とフランチャイズ(FC)契約書の連帯保証人規定について詳しく解説します。
「民法の一部を改正する法律(平成29 年法律第44 号)の施行に伴い,2020年4月1日以降の契約締結に関しては,改正民法が適用されます。
私は業務上,月に10~20件以上,様々な業種のFC契約書やライセンス契約書をレビューしておりますが,実に私のところにくる8割くらいのFC契約書は改正民法に対応していないものとなっております。
事業者として,恥ずかしくない契約書を消費者等に提示することが事業リスクへの姿勢,信用を守る事にも繋がるものと思います。
従いまして,今後,各条項別に解説していきたく思います。
定期的に,自社の契約書をリーガルリスクレビューしましょう。
まずは,「連帯保証人」の規定からみていきましょう。
目次
このような方は,是非確認してください!
<参考資料>
・法務省資料①保証 http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
・法務省資料②債権法改正事項 http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf

<旧民法適用時(2020年4月1日以前)のよくある一文例>
第 〇 条(連帯保証人)
1 連帯保証人は、フランチャイザーに対して、フランチャイジーが本契約上並びに本件店舗を経営する上でフランチャイザーに対して負担する一切の債務につき、フランチャイジーと連帯して履行する責を負う。
2 前項に定める連帯保証人の責任は第△条に基づく本契約更新後も継続するものとする。
但し、フランチャイザーと連帯保証人との間で別途合意が成立した場合はこの限りでない。
3 フランチャイザーは、必要に応じて、連帯保証人の追加又は変更を、フランチャイジーに対して求めることができる。
4 連帯保証人につき地位、身分、経済状態その他重大な変化が生じた場合は、フランチャイジーはその旨を遅滞なくフランチャイザーに通知するものとする。
※上記の一文例は2020年4月1日以降は通用しません。
<結論>
FC契約書以外に格別に個人根保証契約などを締結せず,連帯保証人が個人であり,個人根保証型の場合,改正民法が求める連帯保証制度の義務を遵守していなければ,契約上,連帯保証人は法的に連帯保証契約(連帯保証の合意事項)の無効を主張することができる。
※全無効となるか一部無効となるかは,主張の範囲や普通保証との比較検討の問題となるため,総合勘案となる。
<解説>改正法のポイント
よくある文例ですね。改正前の民法ではこれでよかったと思います。
改正法のポイントをみてみましょう。
■1.包括根保証の禁止(債権極度額の設定義務)
■2.主債務者(FC加盟者)が連帯保証人に対してする情報提供義務
■3.債権者(FC本部)が連帯保証人に対してする情報提供義務
法人保証で,主債務者個人に対して,求償する場合については,別で説明していきます。
まずは,法律の条文を確認。条文背景や趣旨を理解することが必要。
契約書作成&改訂レビューする際は,必ず法律の条文確認をしましょう。
【■1.包括根保証の禁止(債権極度額の設定義務)】
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
| 要点 | レビューポイント | |
| 1. | 条文の趣旨/背景 | ・連帯保証人が,個人の場合には,人的無限責任を負うことに伴う経済生活の破綻のおそれがあるため。これまで,保証人が予想外の責任を負わせられ自殺した事案などの経緯がある。 ・極度額の定めにより,連帯保証人の責任の上限金額が画し,予測可能性を確保するとともに,契約締結時に慎重な判断を求めるため。 |
| 2. | FC契約以外の契約でも同じ論点 | ※下記の契約の場合は,同じく注意です。 継続的売買取引契約,賃貸借契約,貸金(消費貸借)契約,代理店契約,介護施設入居契約,身元保証契約など |
| 3. | 確定的に極度額の設定を書面又は電磁的記録でしなければ,法的効力は生じない | (例1) ×「フランチャイザーに対して負担する一切の債務」 (例2) ×「極度額は賃料(または加盟料,ロイヤリティ,売上)の〇ヶ月分」 ※当該契約書で具体的に極度額がいくらか計算でき,額が確定できれば有効。 |
| 4. | 元本確定期日について,制限規定なし | |
| 5. | 元本確定確定事由(民法第465条の4第1項) | ①. 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 ②. 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 ③. 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。 |
【■2.主債務者(FC加盟者)が連帯保証人に対してする情報提供義務】
(契約締結時の情報の提供義務)
第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
| 要点 | レビューポイント | |
| 1. | 条文の趣旨/背景 | ・条文構造は,限定列挙型。情義的保証による強い要請(圧)への回避策。 ・連帯保証人が,債権者と保証契約を締結する際に,主たる債務者の経済状況を知ることは重要であり,仮に,主たる債務者について,既に期限の利益を喪失している債務があるような場合等は保証契約を締結するや,保証債務の履行を求められるおそれれがあるため。 ・主たる債務者の財産状況,履行状況,担保の設定状況といった主たる債務者の情報について,契約締結時に,連帯保証人に対して,主債務者は適切に開示する必要があるため。 |
| 2. | FC契約以外の契約でも同じ論点 | ※下記の契約の場合は,同じく注意です 継続的売買取引契約,事業用リース契約,賃貸借契約,貸金(消費貸借)契約,代理店契約,介護施設入居契約,身元保証契約(雇用契約時等の書類)など |
| 3. | 情報提供の範囲 | ①.財産及び収支の状況 ②.主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 ③.主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容 ※「保証することによる具体的リスク程度を見誤らせるような事項についての誤認があったかが重要である」と第192回国会衆議院法務委員会会議録16号1項で指摘されている。 |
| 4. | 「財産」と「収支」について | 「財産」と「収支」については,B/SやP/Lで説明されることが想定されている |
| 5. | 義務違反の効果 | ①.主たる債務者が,上記(3)の①~③の情報を提供せず,また事実と異なる情報を提供したことを,債権者が知っている場合や知ることができたときの場合には,連帯保証人は当該保証契約(合意)を取消すことができる。 ②.「債権者が知っている場合や知ることができたとき」とは言えない場合において,連帯保証人は連帯保証契約(合意)に関して,民法第95条に基づき「錯誤」を主張し,連帯保証契約(合意)を取消すことができる可能性がある。民法第95条第3項に従い,表意者に重過失がある場合でも錯誤取消しは認めら得る。 |
| 6. | 表明保証の書面取り付け運用について | 実務では,債権者(FC本部)が,連帯保証人から「資産および収支の状況等について債務者(加盟店)から正確に説明を受けました」との表明保証のような書面や条項で取り付け運用しているケースが多々ある。 しかし,それまでの取引などの諸事情を踏まえると,明らかに説明を受けた事項が虚偽であったと分かるような場面では,かかる書面があったとしても,直ちに債権者が無過失とはいえないと笹井朋昭関係官が指摘している。 たんなる表明保証違反を理由として,保証人に対する損害賠償請求も上記法文の趣旨に照らし許されないとされている。 |
【■3.債権者(FC本部)が連帯保証人に対してする情報提供義務】
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第四百五十八条の三 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
| 要点 | レビューポイント | |
| 1. | 条文の趣旨/背景 | ・主たる債務者が,債務不履行に陥ったものの,保証人が長期間にわたってそのことを知らず,遅延損害金が積み重なって甚大な額になってしまった場合に,保証人が債権者からその履行を求められるのは酷であることから,かかる結果を回避するため。 ・民法第458条の2においては,法人保証の場合も射程される。 ・民法第458条の3においては,個人保証の場合に限られる。 ・「期限の利益を喪失したとき」とは,残金(弁済額)の期限を全てチャラにされ,すべて一括で支払わなければならなくなる状態のこと。せっかくの優遇措置(期限の利益)が奪われる(喪失)ことになるというもの。 |
| 2. | FC契約以外の契約でも同じ論点。下記の契約の場合は,同じく注意です。 | ・継続的売買取引契約,事業用リース契約,賃貸借契約,貸金(消費貸借)契約,代理店契約,介護施設入居契約,身元保証契約などすべての保証契約 |
| 3. | 情報提供の時期 | ・契約締結後の情報提供義務(民法第458条の2) ・主たる債務者が期限の利益を喪失したとき |
| 4. | 情報提供の義務内容 | 【連帯保証人の請求がある場合】 遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供 【主たる債務者が期限の利益を喪失した場合】 ・利益の喪失を知った時から二箇月以内に、期限の利益が喪失した旨を通知 ・通知は,保証人へ到達することが必要 |
| 5. | 義務違反の効果 | 【連帯保証人の請求がある場合】 定めはないが,連帯保証人がする解除や損害賠償請求など,債務不履行の通則に委ねられる。(民法第415条等) 【主たる債務者が期限の利益を喪失した場合】 遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生じていたものを除く)に係る保証債務の履行請求不可 なお,当初の保証人について,相続が発生して,複数の相続人がいた場合は,各相続人に対して通知をなす必要があるとの指摘あり。 |
以上,解説とさせていただきます。法人保証で,主債務者個人に対して,求償する場合については,別で説明していきます。
専門知識がないと難しいですよね。契約書レビューには,専門家が必要だと思います。
これからフランチャイザー本部事業を行う事業者,これからフランチャイジーとして加盟される事業主(事業者)やフランチャイザー本部事業をしているが,改正法対応に改訂していない事業者,法務部署などの方々につきましては,法改正に伴う契約書の改訂をご一考いただき,この記事が参考になれば幸いです。
投稿者プロフィール

-
つばさ城南げんき行政書士事務所 行政書士の宮路(みやじ)です。
時事に関連した法律情報やときどき日常のことを書いていきます。